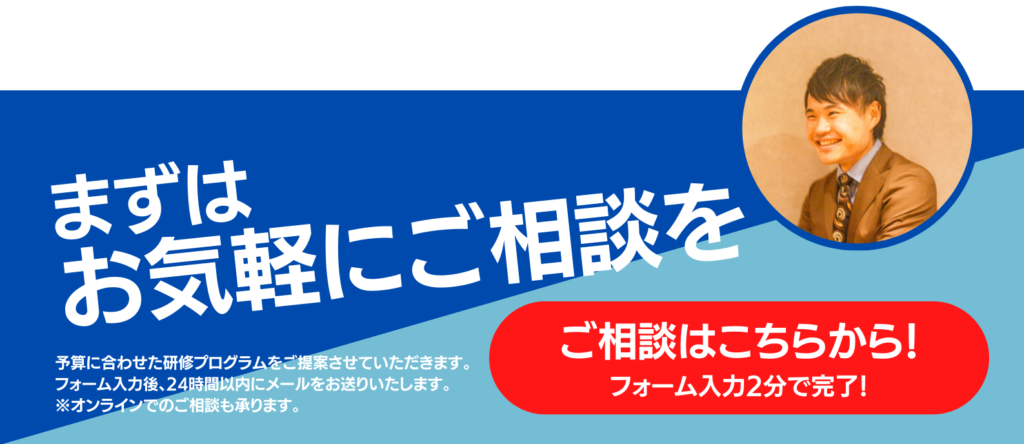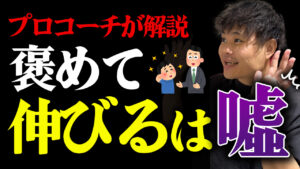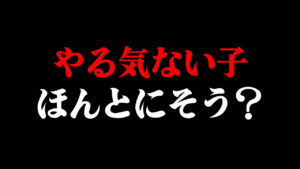「どうせ無理」と言う生徒に、やるべきことと絶対やってはいけないこと
全国の学習塾さんでコーチング研修をさせていただいている、教育コーチングEdcoac代表の沖津です。
私たちは、生徒が「どうせ無理だ」と口にする場面に頻繁に遭遇しますよね。
この言葉、実は失敗や否定を恐れる「防衛反応」なんです。
今回は、「どうせ無理」と言う生徒の心理を掘り下げ、教師が絶対やってはいけない「NG行為」、そして生徒の表情を明るくし、自ら行動を促す「承認」と「問いかけ」という効果的なアプローチを、具体的な事例を含めて紹介していきます。
動画でも紹介しているので、こちらもご覧ください↓
生徒が「どうせ無理」と言う本当の理由
生徒が「私なんて無理」「どうせ無理」と口にする時、
それは単に諦めているのではなく、生徒たちの複雑な心理が隠されています。
生徒自身が、本当に能力がないと考えているわけではありません。
むしろ、過去の経験や周囲の言葉に影響を受け、「失敗したくない」「周りから否定されたくない」という強い気持ちからくる「防衛反応」である可能性が高いのです。
例えば、「失敗したらお母さんにどう言われるだろう」「友達にどう見られるだろう」「先生にどう思われるだろう」といった周囲の目を過度に気にするあまり、
自分自身を守るために無意識のうちに「できない」と反射的に発してしまうことが多いです。
そのため、生徒たちは本能的に自分を防衛しているだけで、「なぜ無理なのか」という明確な理由を説明できないことがよくあります。
「どうせ無理」という言葉は、「できないからやりたくない」という思考に繋がっているということですね。
講師が絶対やってはいけないNG行為
「どうせ無理」と言う生徒に対し、良かれと思ってやってしまいがちな行動の中には、
実は逆効果となる「NG行為」が存在します。
2つ紹介していきますので、『絶対に』やらないようにしていきましょう。
1つ目は、「励ますこと」。
例えば、「君ならできるよ」といった励ましの言葉は、生徒の「無理」という否定的な言葉に対し、それを否定して肯定に転じさせようとする行為です。
これをコーチングでは、「善意の否定」と言います。
生徒が「否定されたくない」という気持ちで発している言葉を、先生が結果的に「否定」していることになってしまいます。
そのため、生徒の防衛反応をさらに強めてしまい、逆効果になってしまうんです。
2つ目は、「無理にプラスに転じさせようとすること」。
生徒がネガティブな状態にあるにもかかわらず、「とりあえずやってみよう」などと、すぐにポジティブな方向へ誘導しようとするのはとても危険です。
生徒の感情を無視して無理に前向きにさせようとすると、生徒は「自分の気持ちが理解されていない」と感じ、さらに心を閉ざしてしまう恐れがあります。
生徒が「私なんて無理だ」と反射的に言ってしまうのは、その理由すら自分では見つけられないほど、本能的に自分自身を守ろうとしている状態です。
そのような生徒に対し、焦って無理やりポジティブな行動を促そうとすることは、彼らの心の準備ができていないまま、さらに追い詰めることにもなりかねません。
これらの行為は、生徒の心理を深く理解しないまま行うと、生徒との信頼関係を損ない、結果的に生徒のやる気を削いでしまう原因になってしまいます。
では、どう接すればよいのか
生徒の「どうせ無理」という言葉に対し、最も効果的なアプローチは、承認と問いかけの組み合わせです。
まず、生徒のネガティブな言葉を、「〇〇ちゃんは今、それができないと思っているんだね」と承認することが重要です。
次に、「今、一番困っていることは何?」など、生徒が自分について考えられるような問いかけを行います。
この方法で、生徒は受け入れられたと感じ、前向きな気持ちへ繋がり、表情や行動が必ず変化していきます。
まとめ
生徒が「どうせ無理」と言うのは、失敗や否定を恐れる自己防衛の表れです。
先生が「励ます」ことや「無理にプラスに転じさせる」のはNG行為となります。
まずは生徒のネガティブな言葉を「承認」し、その後「問いかけ」を通じて生徒自身に考えさせることで、その内なる可能性を引き出し、目標達成へと繋げる意識を持っていきましょう。
教育コーチングEdcoacでは、講師向けのコーチング研修動画を提供しています。
アルバイト講師、新人社員向けの、初級コーチングスキルを完璧に網羅した、動画学習コンテンツです。
こちらのバナーからご覧ください。

研修や講演の依頼、その他のお問い合わせがこちらからお願いします。